運動会屋が発信する運動会に関するコラムです
綱引きは、単なる力比べの競技ではありません。
綱引きは、企業運動会において部署やチームの団結を象徴する競技として常に高い人気を誇っています。
一見単純そうに見える競技ですが、掛け声のタイミングや体の使い方を理解するだけで、勝率が大きく変わります。
今回は、これまで数多くの企業運動会をサポートしてきたプロの視点から、「綱引きで勝つための戦略」と「チームの一体感を高めるコツ」を徹底解説します。
力ではなく、戦略と連携で勝つ。その体験が、きっとチームを次のステージへと導いてくれるはずです。
社内運動会の企画ならお任せください
創業16年、運動会屋はどこよりも真剣に楽しく「運動会」と向き合い続けて来ました。国内最大の運動会プロデュース企業「運動会屋」に是非お任せください!
- 総開催件数2000件の実績から御社にマッチした運動会を企画いたします。
- 社内&部署間のコミュニケーション活性化、社内の士気や気運の向上など社内の問題も運動会で解決の糸口を

綱引きは「力」より「戦略」で決まる
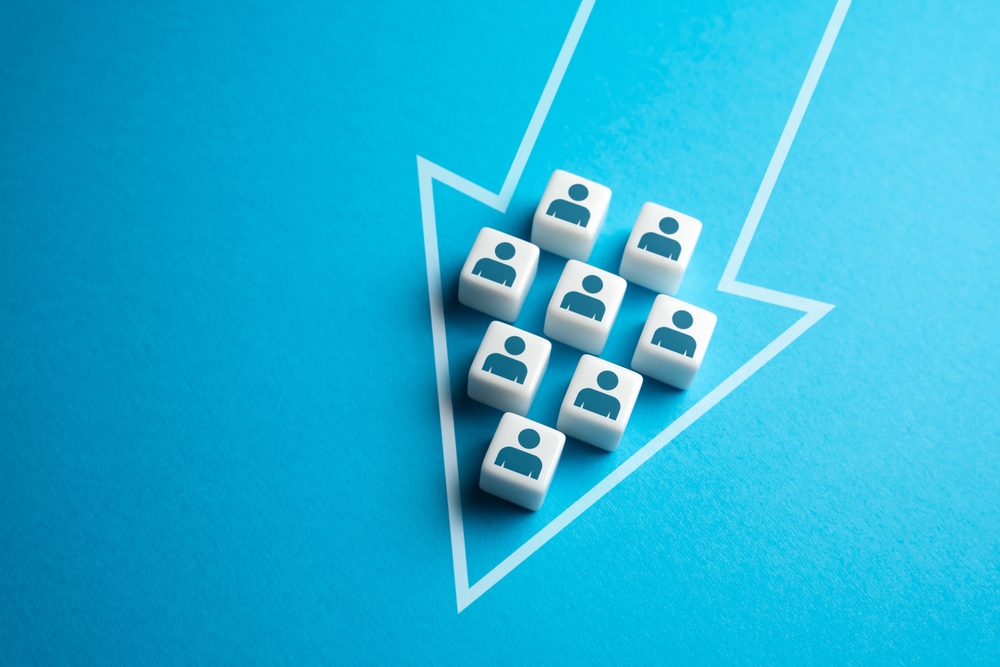
綱引きは、「力」ではなく「戦略」で決まる競技です。ここでは、綱引きの3つの特徴を紹介します。
●綱引きの本質は“全員で一つになる瞬発力”
●企業運動会での綱引きが注目される理由
●チームワーク強化・一体感づくりに最適な競技
それぞれ見ていきましょう。
綱引きの本質は“全員で一つになる瞬発力”
綱引きは、チームワークが生み出す一瞬の力が勝敗を分ける競技です。
つい「体格の良いチームが有利」「筋力の強い人が多いチームが勝つ」と思いがちですが、実際はそう単純ではありません。
重要なのは、「個々の力を足し合わせれば強くなる」という考え方ではなく、全員が同じリズムで、同じ方向に力を伝えられるかどうか。つまり、チーム全員のタイミングの一致こそが、最大の武器なのです。
全員が同じ呼吸でロープを引けたとき、ロープは一気に動き、まるで一つの生き物のようにしなやかに力が伝わっていきます。
綱引きは筋力勝負ではなく、瞬発的な連携がものをいう競技であり、この本質を理解することで、勝てるチームに近づいていきます。
企業運動会での綱引きが注目される理由
今、綱引きは企業運動会の定番競技として、大きな注目を集めています。
その理由は、誰でも参加しやすい公平性と、チームワークを実感できるシンプルさにあります。
年齢や体力に差があっても、姿勢とタイミングをそろえれば勝機がある。実力以外の要素も勝敗に影響するという綱引きの特性は、企業文化づくりや社員同士の交流とも相性が良いのです。
さらに、綱引きは声を出す場面が多いことも特徴です。掛け声や応援によって、普段はあまり会話のないメンバー同士でも、自然に声を掛け合うようになります。
チームワーク強化・一体感づくりに最適な競技
綱引きは、チームワークの強化や一体感づくりに最適な競技です。
その理由の一つが、綱引きには組織の課題を可視化する力があるということです。
たとえば、「指示待ちの人が多い」「声を掛け合う習慣があまりない」チームは、綱引きでも動きがそろわず綱に力が伝わりません。
一方で、「声を出し合える」「互いを信頼して動ける」チームは、自然と勝率が高まります。まさに綱引きは、チームビルディングの鏡とも言える競技です。
また、練習から本番までのプロセスそのものが、職場の雰囲気づくりや信頼関係を深める貴重な時間になります。
綱引きは、単なる運動会の定番種目ではなく、チームの結束力を引き出し、一体感を生み出すための最適なコンテンツなのです。
勝利のカギ①:メンバー配置の黄金バランス

ここからは、綱引きで勝利するためのカギを3つに分けて紹介します。まず勝利のカギ①は、メンバーの配置です。
メンバーを配置する際に、注意したいポイントは以下のとおりです。
●アンカーは体格と精神力のある人を配置
●男女混合チームは“力の偏り”を避けて交互に並ぶ
●背の高い人を中央にして、ロープの高さを均一に保つ
●チーム全体の重心を安定させる並び
一つずつ解説します。
アンカーは体格と精神力のある人を配置
綱引きの勝敗を左右する最重要ポジションが、最後尾に立つアンカーです。アンカーには、体格がよく精神力のある人を配置しましょう。
どんなにロープが動いても踏ん張り続けられる集中力と、精神的な粘り強さを持つ人を配置することで、チームを勝利へと導けます。
男女混合チームは“力の偏り”を避けて交互に並ぶ
男女混合チームで綱引きを行う場合、力が偏らないように男女交互に並ぶようにしましょう。
力のある人が前後どちらかに偏ると、ロープにかかる力のバランスが崩れ、チーム全体の安定性が損なわれます。
男女交互に並ぶことによって、ロープに均等に力がかかり、チーム全体のバランスが良くなります。
背の高い人を中央にして、ロープの高さを均一に保つ
綱引きでは、背の高い人を中央にし、端に向かって背が低くなるように並びましょう。
こうすることで、ロープの高さが均一に保たれ、無駄なく力が伝わり、どのメンバーも安定してロープを引くことができます。
背の高い人が前後に偏ると、ロープが波打ち、力が分散されてしまうため、勝率が下がってしまいます。
また、背の高い人を中央にして並ぶことで、見た目にも統一感が生まれるため、写真映えも抜群です。
チーム全体の重心を安定させる並び方
綱引きでは、チーム全体の重心を安定させるように並びましょう。
重心を安定させるポイントは、競技中にメンバー全員がやや後ろに傾く姿勢を取ることです。
重心が後ろ過ぎると、ロープを引くたびにバランスを崩して転びやすくなります。逆に前のめりだと、力がロスしてしまいます。
試合前に立ち位置を微調整し、全員で軽くロープを引いてみるなど、バランスを確認するようにしましょう。
勝利のカギ②:姿勢と引き方のテクニック

続いて勝利のカギ②として、姿勢と引き方のテクニックについて解説します。
姿勢と引き方で重要なのは、以下のポイントです。
●重心を低くして、体を一直線に保つ
●視線を上に向け、自然に体重をロープに乗せる
●ロープは密着して握る:手の間隔をあけない
●軍手より素手のほうがすべりにくく力が伝わる
それぞれ見ていきましょう。
重心を低くして、体を一直線に保つ
綱引きでロープを引くときは膝を軽く曲げて腰を落とし、重心を低く構えるようにしましょう。さらに背筋をまっすぐに保ち、体とロープを一直線にすることで、引く力を最大限に伝えられます。
逆に、背中が丸まると力が逃げてしまい、足が滑りやすくなります。この基本姿勢を意識するだけで、安定感が大きく向上するでしょう。
視線を上に向け、自然に体重をロープに乗せる
ロープを引くときは、視線をやや上に向けるのがポイントです。うつむいて引いてしまうと、重心が前に移動し踏ん張りが利かなくなります。
正面から上の空間を見るイメージで視線を上げると、自然と体重が後方に移り、ロープに力を乗せやすくなります。
ロープは密着して握る:手の間隔をあけない
ロープを握るときは、手と手をできるだけ密着させて握り、間隔をあけないようにしましょう。
手の間隔が広いと、腕の負担が大きくなり力も分散してしまいます。手と手を密着させて握ることで、腕と体が一体化し、より強い力を安定して伝えられるようになります。
軍手より素手のほうが滑りにくく力が伝わる
綱引きでは、軍手ではなく素手でロープを握るようにしましょう。
安全面を考えると軍手を使いたくなりますが、実は布地は滑りやすく、軍手を使うと力が逃げてしまうことがあります。
ロープは素手で握り、必要であれば軽く滑り止めを使う程度にとどめておいた方が力が伝わりやすくなります。
ただし、長時間の競技では手に負担がかかるため、状況に応じて軍手と素手を使い分けるのが最適です。
勝利のカギ③:掛け声と連携で一気に引く

勝利のカギ③は、掛け声と連携です。
具体的には、以下の3つが重要です。
●「1、2、3!」の掛け声で全員のタイミングを統一
●相手が引いた直後に“カウンター”で引き返す駆け引き術
●息を合わせた瞬発力が勝利を分ける
一つずつ解説します。
「1、2、3!」の掛け声で全員のタイミングを統一
綱引きで最も重要なのが掛け声です。「1、2、3!」の掛け声を出して、全員がロープを引くタイミングを統一させるようにしましょう。
「せーの」よりも、「1、2、3」のようにリズムがはっきりした掛け声の方が、全員のロープを引くタイミングが合わせやすくなります。
タイミングがそろうと、チーム全体の力が一気にロープへ伝わり、相手に大きな負荷を与えられます。
相手が引いた直後に“カウンター”で引き返す駆け引き術
次のポイントは、相手が力を使い切った瞬間を狙う“カウンター”です。
綱引きはロープの奪い合いではなく、タイミングの奪い合いともいえます。
相手が強く引いた直後のわずかな緩みを見逃さず、一気に引き返すことで、勝負の流れを大きく引き寄せられます。
息を合わせた瞬発力が勝負を分ける
全員のリズムが一つになった瞬間、瞬発的な力が最大化され、相手を一気に引き込むことができます。
この一体感こそが、綱引きの勝敗を大きく左右するのです。
勝つチームがやっている!事前準備と意識づくり

勝つチームがやっている、事前準備と意識づくりについて解説します。
●試合前のミーティング練習でチームを整える
●役割分担を明確にする:アンカー・リーダー・声出し担当
●“自分が支える”という意識でリンゲルマン効果を防ぐ
●勝敗以上の価値がある「一体感」を育てる時間を意識
それぞれ見ていきましょう。
試合前のミーティング練習でチームを整える
勝つチームは、試合前のミーティングを欠かしません。
試合前に、掛け声のタイミングや姿勢、足の位置などを簡単に確認しておくだけで、チームの動きが格段にスムーズになり、勝利に近づけます。
役割分担を明確にする:アンカー・リーダー・声出し担当
アンカーは後方で重心を守る、リーダーは前方でテンポをつくる、声出し担当はチーム全体の士気を高めるなど、綱引きには見えない役割が存在します。
それぞれが自分の役割を理解していれば、動きに迷いがなくなります。組織と同じように、誰がどの役割を担うのかを明確にすることが、勝利への第一歩です。
“自分が支える”という意識でリンゲルマン効果を防ぐ
大人数になるほど、「少しくらい力を抜いても大丈夫だろう」と思ってしまう心理を、リンゲルマン効果といいます。
これを防ぐには、全員が“自分が支えている”という意識をもつことが重要です。「一人でも気を抜いたら負けるぞ」とお互いに声を掛け合うことで、チーム全体の意識が高まります。
勝敗以上に価値がある「一体感」を育てる時間を意識
綱引きでは、勝敗だけでなく、チーム全体の「一体感」を育てることを意識しましょう。
綱引きは、社員同士の関係性を深める効果もある競技です。声を掛け合い互いを信頼しながらロープを引く時間は、一体感を生み、職場の空気を前向きに変える力を持っています。
社内運動会の企画ならお任せください
創業16年、運動会屋はどこよりも真剣に楽しく「運動会」と向き合い続けて来ました。国内最大の運動会プロデュース企業「運動会屋」に是非お任せください!
-
- 総開催件数2000件の実績から御社にマッチした運動会を企画いたします。
-
- 社内&部署間のコミュニケーション活性化、社内の士気や気運の向上など社内の問題も運動会で解決の糸口を

まとめ
今回は、綱引きで勝利をつかむための「戦略」と「連携」について紹介しました。
綱引きは単なる力比べではありません。声を合わせ、息を合わせ、仲間を信じて綱を引く…その時間にこそ、社員同士の絆が深まります。
勝敗を超えた一体感を育てられたチームは、職場に戻ってからもそのつながりを持ち続けることができ、日常のコミュニケーションをより豊かなものへと変えていけるでしょう。
ぜひ綱引きを通じて、参加者全員が盛り上がり、一体感が高まるような運動会を企画してみてください。




